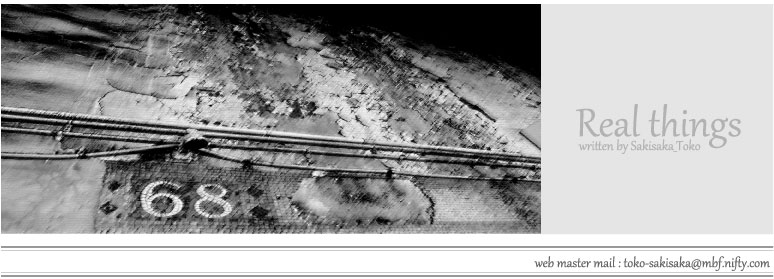
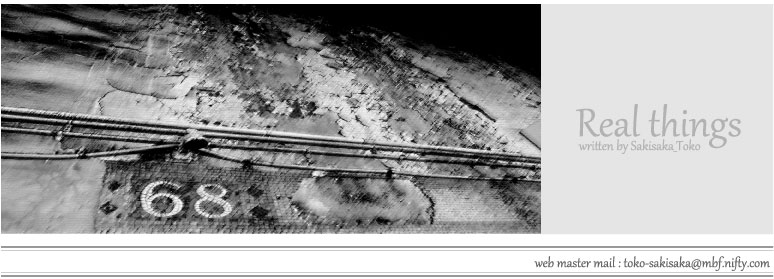
TOP | novel | webclap | weblog | link | ON THE ROAD, TO THE SKY
■ リアル――つまりSM@Pというグループがあってアイドルで、というまんまのキャラクター設定で書いたもの。いずれも連作。
いつか見た遠い空 (K×N 全4頁)
開演前。最後の円陣を組んだとき、向かい側のあいつが俺に必死で何かを訴えようとしていた。それへ軽く頷いて、俺は隣のダンサーさんと、肩を組んだ。いつものように、いままでのように。スタッフで囲む円陣で気合を入れると、その声が届いたらしい客席からどよめきが上がったのが聞こえた。
朝日を見に行こうよ (K×N 全4頁)
お疲れ様、の声に振り向くと、キムラが少しすまなさそうな顔をして片手を上げたところだった。 「あ ―― ああ、お疲れ様……」 ツヨシが一瞬だけ、どう返事をしようかと逡巡しているうちに、隣で着替えの終わったシンゴが笑顔で返事をした。
春にしてきみを離れ (K×N 全3頁)
「花見に行かねぇ?」不意に背後で声がした。まずった、と思いこっそり顔を上げる。楽屋の鏡越しに背後の相手と目が合った。彼は、楽屋の入り口を塞ぐようにドアを背に寄りかかってこっちを見ている。思わず視線を逸らした。
きみまでの距離 (K×N 全4頁)
スターピースねえ。呟いて、シンゴが自分の両手で作ったそれを眺めながら首を捻って呟いた。思案気な顔をして、両手で作ったピースサインをくっつけ表に裏に何度も返している。挙句、よくわかんないから手ぇ貸して、と半ば無理やりにペットボトルの茶を飲んでいたツヨシの手を引っ張り、更に前の座席のゴロウの手も無理やり捻って引き寄せて、スターピースだってば、と自分の指に合わせさせようとしている。ようやく揃った三人分の手で、ピースサインはいびつな星型になった。
花火-HANABI (K×N 全4頁)
じっとりと湿った空気が二人の周りを取り巻いていた。川岸の向こうに遠く、打ちあがる花火が見える。草いきれの青い匂いがあたりに立ち込め、川から渡ってくる時折の涼風が汗ばんだ肌を撫でて行く。
Dawn (K×N 全4頁)
疲れた顔してるね、とスタッフの誰かに声を掛けられたのを笑顔でいなし、楽屋のドアを開けた。がらんとした白い部屋に、入るのは自分だけだ。いつから別々の楽屋を使うようになったのだっけ、と普段は思い出しもしないようなことをふと思って部屋を見回す。今日は週に一度のメンバー全員が揃う収録日だ。ゲストは海外の大物アーティストだと聞いている。きっとキムラとゴロウが大喜びするだろう。その様を思い描いて、ナカイはまた小さく吐息をついた。
Missing (K×N 全6頁)
ほ、と聞こえないように微かに吐息を吐き出して、眠れないベッドからゆっくりと滑り降りた。僅かなベッドの軋みと、肌触りのいいパジャマの衣擦れ。隣で背中を丸めるようにして眠っている相手は起きる気配もない。疲れてんだな、とその横顔を流し見て、テーブルから煙草とライターを握りこむと、ベランダへ通じる窓を開ける。時計はもう2時を回った。
STAY (K×N 全3頁)
前室へ向かう途中だった。ナカイの楽屋の前を通りすがりに、ふっとそのドアを見た。もちろん、無意識だ。いつもは時間まできっちり閉じられているドア。マネージャーでさえ、滅多なことで出入りすることは出来ない。メンバーも、いつの頃からか彼の楽屋だけはノックするのを憚るようになった、その部屋。それがまるで彼が通りかかるのを待っていたようにそっと薄く開いて、その隙間から綺麗な指先がひらひらと招いた。
Le Caillou Bleu (K×N 全12頁)
結局のところ、"楽な年の瀬"なんてものには、縁がないように出来ているらしかった。一年最後の月の頭に封切られた主演映画のために、彼は日本中を飛び回っていた。しかも更なる誘客を狙って、TVへの番宣出演までが次々だった。これまでドラマならいざ知らず、冠番組以外にはメンバーが仕切りを務める番組にしか出演したことのない彼が、滅多に出たこともないバラエティー番組やらトーク番組にひとりで駆り出されるのを、ドラマの収録の合間にちらりと眺めたりした。
ベイブリッジ・セレナーデ (K×N 全4頁)
風が、冷たかった。湿り気のない空気まで凍てついていて、海から吹きつけてくる冷えた温度が頬に痛い。ステアリングを握っている間には気にならなかった冷えが、指先や足先から体中を支配しようとじわじわと這い寄ってくるのをそのままに、遠くに瞬く街のネオンライトを眺めていた。
バタフライ (K×N 全6頁)
くさくさした気持ちでシャワーを終え、ろくに体も拭かないでバスタオルを放り投げた。冷蔵庫から冷やしたコロナを一本。ライムを絞ろうと野菜庫を漁り、そういえば切らしていた、と気づいて、舌打ちして裸足の足先で冷蔵庫のドアを蹴り閉める。ジーンズを引き上げてスタンドライトを点けると、突然大きな影がふわりと目の前を横切った。
Dynamite (K×N 全6頁)
ずっとつきまとって離れない、誰かの視線。その視線の主が、”あいつ”だと、気がついたのはいつ頃だったろう。仕事の打ち合わせ中に、番組の収録中に、ライブのリハーサル中に。始めはおずおずと俺を追いかけるだけだった視線が、やがて少しずつ大胆になり、熱を帯びたものになるにつれ、俺は”あいつ”と一緒にいられなくなった。まるで虫ピンで押された蝶みたいに。あいつの視線がそこここで俺を射抜くたびに、俺は立ちすくんで動けなくなる。もがいてももがいても、あいつの視線は俺から離れない。なにが言いたい。なにがしたい。まとわりつく視線は、いつしか俺自身も絡めとり、あいつの訳のわからない熱視線の狂熱にじりじりと炙られて。導火線に火がついていることに、俺自身も気がつかないでいた。危うい、爆発の瞬間はそこまで来ている。
青いイナヅマ (K×G 全2頁)
漂ってくる煙草の煙に、仰のいて目を開けた。皮膚の下、一ミリのところををまだ何かが這い回ってる。ぞわぞわと何かが。快感のような、悪寒のような、そんな感じ。身じろぎすると違和感が高まる。寝返りを打った瞬間に、違和感の出所から濡れた感触が伝った。僅かに上体を起こした格好で肘をついている背中に手を伸ばしかけて、やめた。
Flapper (K×G×N 全6頁)
じゃ、準備よければ頭から通しまーす。マイクの声がかかり、舞台監督が合図を待つように首を伸ばしてあの人の方を窺った。汗を吸いすぎてすっかり役に立たなくなったタオルを放り投げ、ドリンクボトルから一口水を含む。汗の滴る髪を片手で後ろに掻き上げながら向き直り、彼がゆっくりセンターに戻る。Tシャツをたくし上げた袖口から覗く、薄い筋肉のついた滑らかな肩から二の腕のライン、なんてことはないどこにでもあるデザインなのに不思議とウエストから腰骨のラインを強調してほっそりみせるハーフパンツに包まれた下肢、素足にダンスシューズを履いたすんなり伸びた足。
退屈な日曜日 (K×N 全4頁)
珍しく日曜日が暇だった。仕事もないし、予定もない。仕事人間としては、こういう時が一番困る。誘おうにも人目はあるし、第一いきなりの誘いなんかに乗ってくれる相手もいない。スケジュール帳を意味もなくめくり、丸々空いた空白の一日をどうしたものか、とため息をつくしかすることがない。(昼風呂にでもゆっくり入って、昼酒でも飲んでやろうかな)発想が既にオヤジモードなのは、先々月に誕生日を迎えて、もはや四捨五入で大台に乗ることを考えれば致し方ない。時計を見るとまだ10時過ぎだ。一日が長い。とにかくもう一眠りしてから考えよう、と決めてシーツの間にもぐりこんだと同時に玄関からガチャガチャと鍵を開ける音が響いてきた。
<09'キーワード3題でSS> モーニングムーン (K×N 全2頁)
明け方近く、目を覚ますと目の前に丸まった背中が見えた。昨夜は眠りに落ちるまで、確か髪を撫でていたはずなのに、結局これだ。少しだけ身体を起こしてみると丸まった身体は水色の大きなイルカを抱きこんでいる。(ちぇ。抱きつく相手が間違ってるっつーの)また横たわって、短い後ろ髪を指先で突いてみる。そういえばこんな短く刈られた髪は随分長く見ていなかった気がする。十代の頃以来、かも知れない。(ハチャメチャだった、もんな。俺ら)短く柔らかな感触があの頃をふと思い出させた。
<09'キーワード3題でSS> 夜凪 (G+N 全2頁)
深夜も過ぎた横浜の街は昼間の賑わいとは無縁な静けさで僕を迎えた。24時間営業の駐車場を探して車を入れ、無意識の動作で携帯を上着のポケットにすべり落とす。歩いて、海に沿った公園へ向かう。時折カップルとすれ違うが、薄暗い灯りの下では面が割れないらしく誰にも声を掛けられずに済んだ。公園の手すりから眺める海は暗く、ホテルの明かりと高層ビルの非常灯が乱反射するぐらいで、水面の揺れさえ定かではない。春の終わりの風が時折潮の匂いを運んできて、僕はそれをゆっくり吸い込んだ。
<09'キーワード3題でSS> ロマンセ (N×K 全2頁)
頭が重かった。手足もだるい。ことに、腰の辺りが。二日酔いだ、と意識した途端、胸の辺りがむかついた。カーテンを引いていない外はまだ暗い。昨夜は飲みすぎた、と思いながらそろそろと寝返りを打つと、ヘッドボードに背中を預けながらベッドサイドランプで台本を読んでいる横顔が見えた。
さくらの花の咲く頃に 〜 "moon"シリーズ・1 (全1頁)
目の前が突然ハレーションを起こした。後頭部を殴られるような激しい痛みが断続的に襲ってくる。「 ―― ッ!」思わず息を呑み、両手で顔を覆う。まただ、と頭の隅を他人事のような意識が過る。自分の中に、もう一人別の意識を持った人間が居るようだ。沸いてきた苦い唾を呑み込み、痛みの過ぎるのをひたすら待つ。一瞬の激痛が永遠に感じられた。冷たい汗が背中を流れていった。
Cresent moon 〜 "moon"シリーズ・2 (全1頁)
「帰ろ」
「送る」二人同時に手を差し出した。彼は困ったように並んだ俺たちの顔を見比べて、少しの間黙り込んだ。収録が終わり、珍しく俺とキムラくんの誘いと天秤にかけた彼は、ちょっと俯いて自嘲気味に笑うと俺の手を取った。交わす言葉も少なく、二人で肩を並べて駐車場に降りて、彼は黙って乗りなれた仕草で俺の車の助手席に乗り込んだ。「これからどうする?」俺の問いかけに、彼は左手の爪を噛んだまま答えない。「ねえ、ナカイくん」聞こえている癖に。俺はこっそり口の中で呟いてみる。聞こえているのに、聞こえない振り。キミの、得意技。都合が悪かったり、自分の思うようにならないと、キミは決まって知らない振りをする。気が付かない俺が、ひとりで右往左往するのを楽しむように。……何だか、ムカツク。
横目で隣をちらちら見ながら、大きくハンドルを切った。
キスが欲しい 〜 "moon"シリーズ・3 (全1頁)
2日に渡る、長い生放送の収録が終わった。 人込みの向こうで、疲れた表情を笑顔に隠した想い人が笑っていた。丸一昼夜半、ろくな仮眠さえ取らずに重責をやりおおせたすがすがしさは、その表情からは伺えない。淡々と長い仕事をこなして、淡々と「お疲れさん」の声を受けて、彼はいつもと変わらずにそこにいる。( ―― 一度も、俺を正面から見なかった)視線の主を感じないはずはないのに、彼はこちらをちらとも見ない。
Wipe out 〜 "moon"シリーズ・4 (全1頁)
彼がいなくなった。 突然の出来事だった。
ROSE 〜 "moon"シリーズ・5 (全1頁)
楽屋のドアをくぐると、まるで今さっきまで泣き腫らしていたような瞳で彼が振り返った。「 …… おつかれさま」 「 ―― おつかれ」ネクタイを緩めながら近寄ると、彼は相手が俺だったことに安心したように、また少し仰向いて椅子の背にその小さな頭を預けて目を閉じた。「どうかした」 「 …… ちょっと疲れたかな。ストレスが目にきてるってサ」低い、ほとんど囁くような声で彼が返す。「じゃあ、車とか運転もムリでしょう」 「するなって言われた ―― 言われなくてもムリだわ、仕事中はともかく、痛くて目え開けてらんねえもん」 「医者は」 「ストレスの原因を取り除くのが回復の早道 ―― だってよ。んなもん、ねえっつうのに」…… 嘘つき。「わかんねえ、っつったら、仕方なしなし、目薬だけくれてさ。あまり酷使しないように、不規則な生活だけでもストレスになりますよ、だって。あんまり馬鹿らしいから、二度と行かねえ」閉じられた瞳の上に、手のひらを乗せる。彼がくすぐったげに身をよじる。
秋の気配 〜 "moon"シリーズ・6 (全1頁)
そのシーンに出くわしてしまったのは、ほんの偶然だった。自分より先にスタジオを出たはずだったのに、彼の姿がどこにも見えなかった。(先に車に行ってろって言ったのに …… )記憶障害が出てから、とみに子供っぽさが表に現れつつある彼だ。その彼の面倒を見ている俺は、恋人というよりはもはや保護者のようで。一から十まで目の離せない子供を抱える親の気持ちが良くわかる、と彼がスタジオを大人しく出て行った後でツヨシにこぼしたばかりだった。「あ、ツヨぽん、キムラくん知らない?」 「さあ …… 控え室じゃないの? ―― お先に」 「ああ、お疲れ様 …… 」事情を知っている数少ないひとりのツヨシは、どちらかといえばナカイくん派で俺とタクヤに冷たくなった。ことに、事件のあとでは、あからさまにタクヤを避けている。(許せないんだろうな、タクヤも俺も)
everything 〜 "moon"シリーズ・7 (全1頁)
いつまでも飽きもせずに海を眺めている背中に、そっと近寄って手を触れた。遠く水平線に、オレンジ色の燃えるような太陽が落ちていこうとしている。レンブラント光線が、白い波頭を輝かせていた。「 …… もう、戻ろう?いつまでもこうしてると、体が冷えてまた熱出すよ」彼は聞こえているのか、熱心に落ちて行く夕陽を眺めて、振り向きもしない。「ねえ、ナカイくん」もう一度、今度は気持ち力を込めて揺さぶると、彼は唇を尖らせた表情で少しだけこっちを振り向いて、しぃっと指を立てた。「 ―― もう、ちょっと」波の寄せて返す音と、名前も知らない鳥の鳴き交わす声、余計な雑音などひとつも入り込まない世界で俺たちはふたりきりだった。「もうちょっとで、日が沈むから …… 」俺は仕方なく手にしたバスタオルで彼の肩をくるむと、その傍らに腰を下ろした。
a place in the sun 〜 "moon"シリーズ・8 (全1頁)
一人で目覚める夜更けの部屋。もう慣れてしまった、一人きりのベッド。誰かとぬくもりをわけ合う夜など久しくなくて、水底のようにしんと静まり返った部屋で覚えてもいない夢にうなされて目を覚ます。覚醒と共に、自分の頬が生理的な涙に濡れていることにぞっとした。窓の外から、波の音が聞こえている。カーテンを閉めずに眠った窓からは、星明りが差し込んでいる。隣家とさえ1Kmは離れているこのコテージに暮らしているのは、俺とモリだけだ。無性に喉が渇いて、だれが咎めるわけでもないのに物音を立てないようにベッドを降りる。星明りの差している部屋は、蒼い光で満たされていた。
eternaly 〜 "moon"シリーズ・9 (全1頁)
緊張感をはらんだ沈黙が、そこに居合わせた俺たちの間に張り詰めていた。どこかうつろな固い表情のゴロウと、その隣でゴロウの膝に軽く手をおいて俯き加減のツヨシ。今ひとつ事態を把握していないキムラくんと、俺。「 ―― 連絡、入ったって」囁くような低い声で、多分この中では一番冷静な立場にいるのだろうツヨシが、俯いたまま言った。
Innocent sky 〜 "moon"シリーズ・10 (全1頁)
ふと窓の外に目をやると、陽光の照り返しを浴びて眼下一面の雲海がまぶしい白に輝いていた。さっきの機長の案内では東京地方は曇りだと言っていたが、雲の上ではどうやら関係がないらしい。どこまでも続く雲海の白が、ふいにあの日の暗い絶望を思い出させた。
永遠の一秒 〜 "moon"シリーズ・11 (全1頁)
あの日。彼は俺の手を取らずに、一人で消えた。俺は立ち去る彼の頼りない後姿を、見えなくなるまでじっと立ち尽くして見送るしか術を持たなかった。彼は、俺との未来さえも、選んではくれなかった。戻ってきたのは、平穏な日常。平和で、これといった事件もない代わりにあの日々のように胸を絞られるほどの切ない愛情を試されることもない、静かで穏やかな家族との毎日。さらさらと流れていく時間の中で、俺はふとした空白に彼と過ごした不思議な日々を思う。時間よ止まれ、と祈るように思った、あの永遠の一秒を ――
the end of the world 〜 "moon"シリーズ・12 (全1頁)
それから半年以上の月日が流れた。誰もが、あんな事件などなかったように口をつぐんで目を逸らしたままだった。誰もが、細心の注意で彼の名前を口にしないように努めていた。誰もが、彼の行方を探さなかった。……かれ、以外は。
Vanishing 〜 "moon"シリーズ・13 (全1頁)
「……シンゴ、ちょっと」背中からマネジャーの声がした。振り返る。いつもなら、鉄面皮の仮面の下に押し込めて、チラリとも内心を窺わせたことのない彼女が、躊躇うように視線を泳がせて俺を手招いていた。三人の番組撮りが終わった直後の控え室。ゴロウとツヨシのスケジュールはもう上がりの筈で、俺だけがレギュラーのラジオ番組の収録が残っている。
Love letter 〜 "moon"シリーズ・14 (全1頁)
元気でいますか。どこにいますか。何をしてますか。ふたりでいますか。……幸せ、ですか。
ハナミズキ 〜 "moon"シリーズ・15 (全1頁)
今日も、彼は太陽の匂いをさせながら満足げな顔で日の高いうちに戻ってきた。今日はちょっと遠出、と言いながら台所で何かシャクシャクと掻いている音がする。そのリズミカルな音をぼんやり聞いていると、意識がすうっと遠くなって眠りに引き込まれそうになる。(だめだって。今日こそ言わないと。今日こそ)心の中で自分を叱咤しつつ、起き上がるのもままならない自分を情けなく思いながら、ぼんやりした視界の中心にある白く光るようなシャツの背中を眺めた。
■ パラレル――キャラクターだけ借り、人物設定その他は全てオリジナル。ヤツらがドラマでもしてるような感覚でどうぞ。
夏の終わり (K×N 全7頁)
あれから何時間、ぼんやりとしゃがみこんでいたろう。太陽は大分西へ傾いて、影が長くなっていた。次の町にたどり着くにしても、誰か助けを探すにしても、ここでこのまま座り込んでいてはお話にならない。ドライアップになる前に、歩き出さなくては。そう思い始めたとき、けたたましいクラクションと物凄い砂煙を伴って、一台のトレーラーが彼のお手上げのレンタカーの隣に停車した。
ベイビーブルー (K×N 全15頁)
――おまえ、家出か。 客を引くのにも飽きた明け方近い新宿の街で、マサヒロは彼に出会った。マサヒロより二つ三つ年上に見える、黒っぽいスーツに派手な色のシャツを合わせ、ボタンを多めにあけた胸元からシルバーのチェーンを覗かせた日焼けで黒い男。この界隈では、こんな格好のヤツは地回りのチンピラかホストクラブの売れないホストくらいだろう。キャバクラのスカウトだってもう少しは見られる格好をしている。マサヒロは、といえばこちらもあまりに素っ気ない丈の短いTシャツにきりきりに細身のブルージーンズで、唯一のアクセサリはこの間の客が気まぐれにくれた細い指に似合わないシルバーの凝った意匠のごついリングだけだ。東京に出てきて3ヶ月になるが、その3ヶ月で身についてしまった荒淫ですさんだ風情が、実年齢よりも彼を老けて見せている。”商売”にはその方が警戒されずに済むことも多いけれど、よく「ハタチ過ぎくらい?」と尋ねられる彼が、実はまだ18にもなっていないなどとは客の誰もが思わないに違いない。
君が人生の時… (K×N/S×N 全13頁)
明け方の街に漂う、潮の匂いが好きだ。少しも綺麗な海ではないが、明け方にその匂いを嗅ぐ時だけ少し気持ちが落ち着く気がする。日が昇れば饐えた生臭い匂いを漂わせるだけのドブ水も、その一時だけは遠いどこかの青い海と同じ水なのだと想像することの出来る、潮の香り。それを胸一杯に吸い込むと、ようやく生き返ったような気分になる。俺は、この街の汚れた海しか知らない。
Esrimita ferice〜幸せの果て (オールスター 全55頁)
いつも5人で居た子供たちだった。両親を知らない子供。母親をなくした子供。母親にも父親にも、欲しがられなかった子供。繰り返しの暴力の末に捨てられた子供。目の前の母親の死に立ち会った子供。それぞれがそれぞれの事情を抱えてその施設に集められ、いつの間にか5人で寄り添うようになった子供たちだった。
Triangle (S×K×N 全14頁)
午後の空港は混んでいた。椅子に背中を預け、見るともなしに目の前を過ぎていく人を眺める。 過ぎていく人は皆忙しそうで楽しそうだ。
大きなスーツケース、賑やかな会話。ホラ急がないと駄目だって。待ってよ、パスポートどこにあったかな。ねえ、スーツケースからあれ出した?向こうで着替える着替え。向こうって季節何だっけ、もう暑いの?雨季って言ったってさあ… エトセトラ、エトセトラ。ぼんやりしていると、行き交う人の声に圧倒されそうだ。ふと、どこかから懐かしい香りがした。ふんわりと鼻先に香る、柑橘系のコロン。
<リーマンナカイとプーキムラ シリーズ>
どんないいこと (K×N 全3頁)
今月に入って5件目になる、再就職の面談。漸くの思いでそれを終えて、窮屈でしようのないネクタイを緩めながら駅の改札を人波に押されて通り抜けた。梅雨の終わりを感じさせる蒸し暑さと、駅を出た途端に吹き付けてくる不快な熱気。 時計は5時半を指している。
彼のとなりの俺の場所 (K×N 全2頁)
おはよう、と目の前の顔が笑った。大抵、ちゃんと定時に出かける勤め人の彼のほうが、俺よりも早くに目が覚めている。前の晩にどんなに過ぎたセックスをしても、翌朝の彼はそんなことなどかけらも伺わせない清潔さだ。彼は笑って俺の寝顔を覗き込み、それから離れた。「なに?まだ寝惚けてる?」鏡も見ずに、器用な手つきでネクタイを締めながら、彼がもう一度俺の上に屈みこむ。「……見惚れてる」「―― ばかか、目え覚ませ」ピン、と音がするくらい指でおでこを弾かれた。
しようよ (K×N 全4頁)
午前1時を回って最後のラッシュに込み合う電車に、疲れた体をもまれて、ようやく戻ってくる自分の部屋。階段を上がる前にふと窓を振り仰ぐ。 (―― 来てない、か) 独身者が多いアパートではあるけれど、平日のこの時刻はほとんどの窓に明かりがついている。人の気配がないのは、3階の一番角の部屋……ナカイの部屋だ。苦いため息をついて、ナカイはネクタイを緩めながら階段に足をかけた。
Summer Gate (K×N 全3頁)
「なぁなぁ、今度の週末なんだけどさぁ」リビングの椅子をひっくり返して反対に座り、背もたれに載せた腕に顎を乗せてタクヤは少しばかり甘える調子で声を掛けた。食べかけの朝食がテーブルに散乱している。時計をちらりと見て、向かい合せに座っていた相手が新聞を畳んで立ち上がった。「週末?」「そう、週末。土曜日。知ってる、3つ先の駅からちょっと行った先の河原で……」得意そうにタクヤが言いかけた言葉を、クロゼットに向かった相手は無情に遮った。
夏日憂歌〜Summertime blues (K×N 全3頁)
お疲れ様でした、と隣りで立ち上がった女性モデルに声を掛けられて、お疲れ様、とメイクを落とす手を止めると頭を下げ返した。ドアひとつ隔てたスタジオでは機材を片付けているのだろう、人の声がしている。それを気にするように彼女は一度振り返ってから、あのお、と一歩タクヤの方へ近づいた。 「あのお……キムラさん、このあとお暇ですか……?」またか、と思った。いつものことだ。
ひと駅歩こう (K×N 全3頁)
いつもは車であっという間に通り過ぎる道を、ふと降りて歩く気になった。 次の駅まで一駅だけささやかな散歩道。覚えのある線路沿いの道を、鼻歌混じりに歩く。道端に月見草の花が揺れている。 さっきまでの夕立に濡れた、地面の匂いと夏草の匂いがした。
<Valentain special 05'> 僕は君を連れて行く (K×N 全6頁)
営業強化月間の営業マンは、忙しい。それが年度末を控えていれば尚更だ。これで5日連続タクシー帰宅かな、とタクシー券の残りを確かめてマサヒロはため息をつく。タクシー券とは言っても半期に一度、30枚綴りの冊子が一冊だけ配布されるそれは、上限1000円のシロモノだ。新社屋に移転したせいで通勤時間は倍近くになり、深夜タクシーを使えばタクシー券だけでは到底足りない距離 ――― 休日も出勤で、疲れの抜ける暇もなく、ストレス解消の場所も相手もなく、企画会議、プレゼンテーション、販促会議に客先回り、ノルマの山と同僚の愚痴と上司のぼやきと得意先のクレーム処理、競合会社との胃の痛くなる駆け引きに接待、目まぐるしく回るルーティンワークの毎日。
十六夜の夢 (K×N 全3頁)
その日のタクヤは、少しばかりふてくされて家路をぐだぐだと辿っていた。タクヤにしては長続きした、引っ越し屋のバイトの最終日。受け取ったバイト料で恋人へ土産のビールとつまみでも買って帰る予定が最後の最後で荷主からついたクレームで時間を食った。しかもその責任を、組んだ社員のリーダーにヤツ当たられ、無言で険悪なままトラックで車庫に戻ったのは予定よりも3時間も過ぎてから。ぶーたれた気分のまま駅のコンビニで週刊誌の立ち読みをハシゴし、ついでに駅前のピロティに屋台を出している顔馴染みのヤンチャな悪オヤジに掴まるままビールをがぶ飲みして、気がつけば時計の針はもうすぐ日付も変わる時刻になっていた。
<09'キーワード3題でSS> 楽園の花 (K×N 全3頁)
今年の夏休みなんだけどさ。タクヤが突然言い出したのは、まだゴールデンウィークも終わったばかりの頃だった。雑誌の専属モデル契約をしてからのタクヤは、妙に忙しい。かと思うと意味もなく長い休みがあったりする。当然、堅い勤めのサラリーマンであるマサヒロと、休みが重なるのは稀だ。その証拠に、せっかく連休だったマサヒロを尻目にタクヤはグラビア撮影だといって海外へすっ飛んで行ってしまった。それがマサヒロの不興を買ったのは言うまでもない。